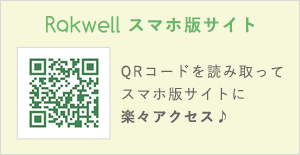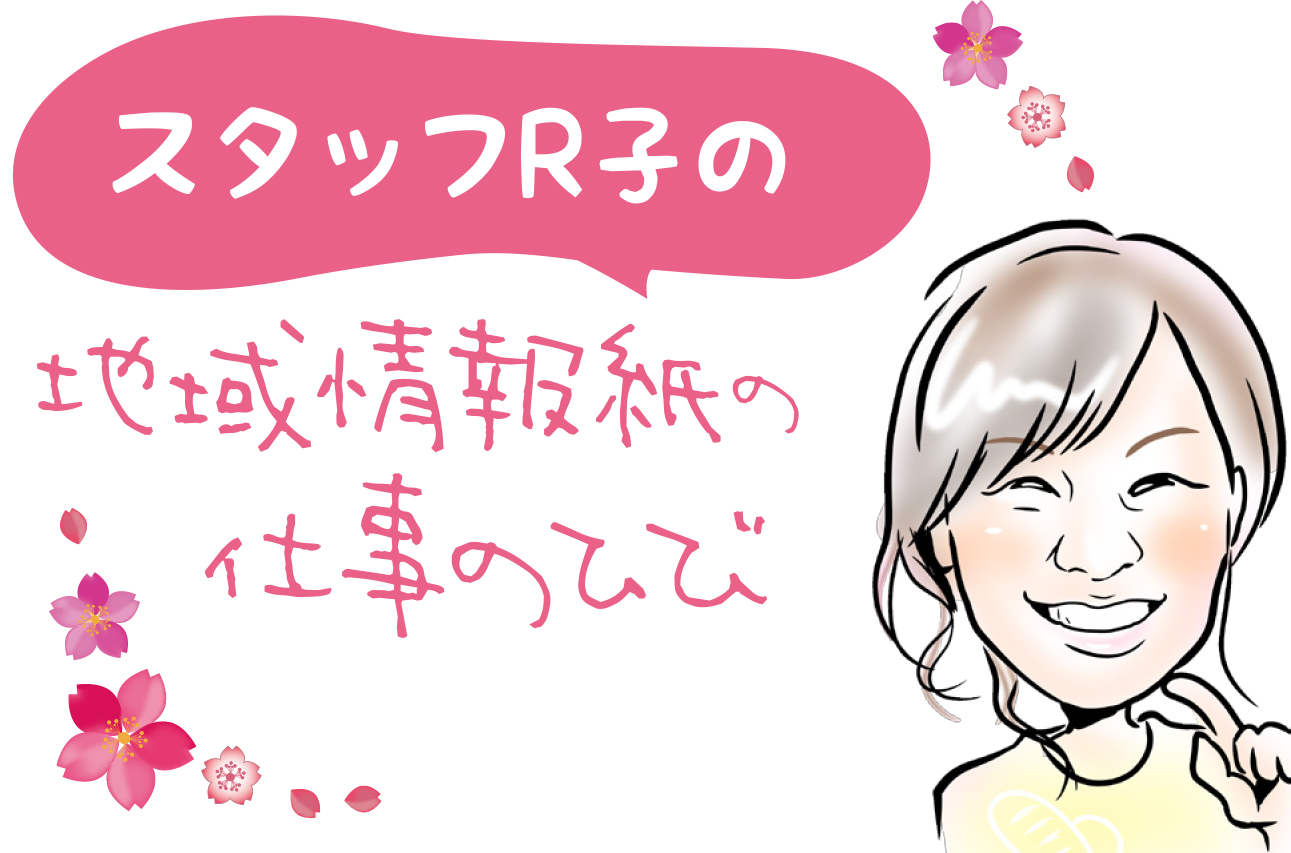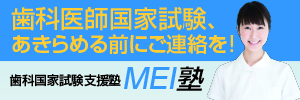「今」と「昔」が響き合う、懐かしくて新しいまち
南海と近鉄、大阪の主要私鉄両線が乗り入れる河内長野は飲食店やショッピングセンターなどのビルが建ち並び、人や車の往来も多い繁華な場所。ところが、ものの数分も歩けば、景色は一変。平安時代から高野山への参詣道として栄えてきた「高野街道」はじめ、さまざまな史跡、神社仏閣が点在し、情緒ある街並が広がります。
檜尾山 観心寺

平安時代の初め、大同3(808)年に弘法大師空海がこの地を訪れ、境内に北斗七星を勧請。弘仁6(815)年、衆生の除厄のために本尊如意輪観音菩薩を刻まれて寺号を観心寺と改めました。梅、桜、紅葉の名所としても知られています。
天野山 金剛寺

天平年間(729〜749)、聖武天皇の勅願により行基菩薩が開創。八条女院が高野山より真如親王筆の弘法大師御影を御影堂に奉安し、女性が弘法大師と縁を結ぶ霊場とされたことから、「女人高野」とも呼ばれています。室町時代の庭園は四季を通じて美しい。
延命寺

弘法大師が地蔵の石仏を刻んで御本尊としたのが起源と伝えられています。紅葉の名所としても有名で、とくに樹齢1000年ともいわれるカエデの老木は、夕陽に映える美しさから「夕照の楓(ゆうばえのかえで)」と呼ばれ、府の天然記念物に指定されています。
岩湧寺

1300年以上前、修験道の開祖役行者が開基した寺で、山伏たちの修験道場として栄えました。大日如来坐像と多宝塔は国の重要文化財、境内のカヤの大木は市の天然記念物に指定。岩湧山の中腹に位置するため、多くのハイカーが登山の途中、参拝に訪れます。
千代田神社

江戸時代には、天神社、天満宮と呼ばれていたが、明治時代には北山神社、菅原神社と呼ばれ、菅原道真を主神としていました。明治40年(1907年)に近隣の木戸神社と伊予神社が合祀され、昭和43年(1968年)に現在の神社名である千代田神社となりました。
10月の2
河合寺

643年、蘇我入鹿によって建立されたと伝えられています。かつては塔頭が24坊もあり、河内三大寺の一つに数えられた。木造多聞天立像、木造持国天立像、木造千手観音など平安時代の仏像は国指定の重要文化財。寺の周辺は桜やアジサイの名所でもあります。
興禅寺

行基によって767年創建。本尊の木造阿弥陀如来坐像は平安期作で国の重要文化財に指定。境内の池に咲く斑蓮(まだらはす)が有名で、創建当時の植栽とか。7〜8月にかけて大きく真っ白な蓮が早朝から咲くため、多くの見学者が訪れます。